「死者の奢り」は、大江健三郎の文壇デビュー作です。大江は『

「死者の奢り」(『死者の奢り・飼育』所収)
1959年初版発行
(この記事はかなり長くなりました。
あらすじ
「僕」は大学医学部の事務室に行き、
解説
・完璧な物体たち
「僕」は水槽に浮かんでいる死者たちを見て、

写真の液体が濃褐色じゃないことには触れない方向でオナシャス。
これらの死者たちは、死後ただちに火葬された死者とはちがっている、と僕は考えた。 水槽に浮かんでいる死者たちは、完全な《物》の緊密さ、 独立した感じを持っていた。死んですぐに火葬される死体は、 これほど完璧に《物》ではないだろう、と僕は思った。 あれらは物と意識との曖昧な中間状態をゆっくり推移しているのだ 。それを急いで火葬してしまう。あれらには、 すっかり物になってしまう時間がない。(pp.17-18)
アルコール水槽に保存されている死者たちには、
・裏切られた好意
「僕」は死体処理のバイトをした後、全身に充実感を覚えます。「

仕事をした後の快活な生命の感覚が僕の躰に充満した。指や掌に風があたり、それが官能的な快感を惹きおこした。 指の皮膚が空気を順調に呼吸している、と僕は思った。(中略) 健康さが、僕の躰の中で幾たびも快楽的な身震いを起した。 僕は靴紐を結びなおすために躰をまげ、 自分があれらの死者たちから、はるかに遠くにいる、 と満足して思った。 自分の躰の柔軟さが喉にこみあげてくるほど感動的で新しいのだ。 (p.27)
生を充実させた「僕」は附属病院前の坂を下っている途中で、
僕はそのまま数歩あるき、少年の顔を覗きこんだ。それは、少年ではなかった。固定された頭をまっすぐ立てたまま、 血管の膨れた額をした中年の男が、 苛立ちと怒りにみちた眼で僕を睨んでいた。(p.28)
「僕」は生者であり、
・サルトル的な不条理
自分の好意を裏切られた「僕」は、精神的なダメージを受けます。
僕は茫然として立ってい、僕の躰一面に、急激にものうい疲れが芽生え、育った。あれは生きている人間だ。 そして生きている人間、 意識をそなえている人間は躰の周りに厚い粘液質の膜を持ってい、 僕を拒む、と僕は考えた。 僕は死者たちの世界に足を踏みいれていたのだ。 そして生きている者たちの中へ帰って来るとあらゆる事が困難にな る、これが最初の躓きだ。(p.28)

初期の大江はサルトルの影響を受けているとよく言われます。
・今後の大江文学の予言!?
「僕」は他人との交流に期待を持ち、裏切られました。「
「妊娠するとね、厭らしい期待に日常が充満するのよ。おかげで、私の生活はぎっしり満ちていて重たいくらいね」 (中略)「十箇月私が何もしないでいたら、それだけで私は、ひどい責任を負うのよ。私は自分が生きて行くことに、 こんなに曖昧な気持なのに、 新しくその上に別の曖昧さを生み出すことになる。 人殺しと同じくらいに重大なことだわ。 唯じっとして何もしないでいることで、そうなのよ」(p30)
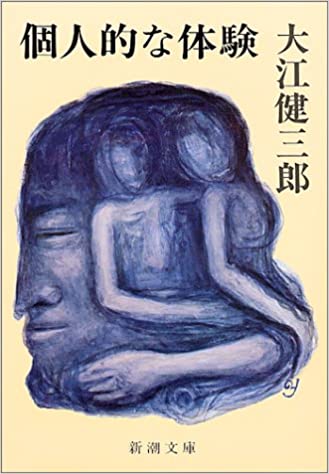
「女子学生」は妊娠していて、子供を堕そうと思っていましたが、
・死者の条理、生者の不条理

「死者の奢り」
「意識がない者は条理に沿っていて、
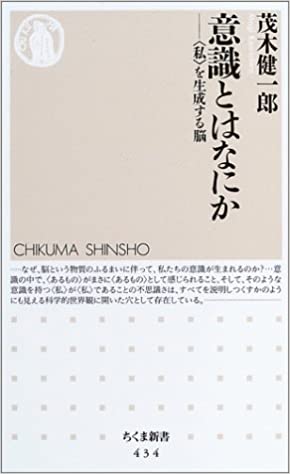
茂木健一郎は『意識とはなにか』で、
しかし、意識を持った生者たちは、完璧な《物》
〈関連記事〉
↑この方の考察は参考になりました。モロに影響を受けました。