皆さん、ごきげんよう。
本日は緊急事態が発生しましたので、速報をお伝えします。
なんと、私の人形(名前:無為美ちゃん)が、
世界各地で物価のインフレが続き、
私の家庭内でも人形の美しさのインフレが止まらず、
試論:音楽の演奏時間が短くなると、一体どんな問題が生じるのだろうか?
テオドール・アドルノは、
しかしアドルノのポピュラー音楽批判論文“On Popular Music”は、
シリアス音楽には全体的な計画性がある
アドルノは“On Popular Music”で、「ポピュラー音楽(popular music)」と「シリアス音楽(serious music)」を区別している。
 テオドール・アドルノ(1903~1969)
テオドール・アドルノ(1903~1969)
シリアス音楽は、(ポピュラー音楽とは)

(ベートーヴェンの第五交響曲のスケルツォの場合、)
シリアス音楽はポピュラー音楽に慣れた現代人には高尚すぎると思
ポピュラー音楽は標準化され、気晴らしのために使われる
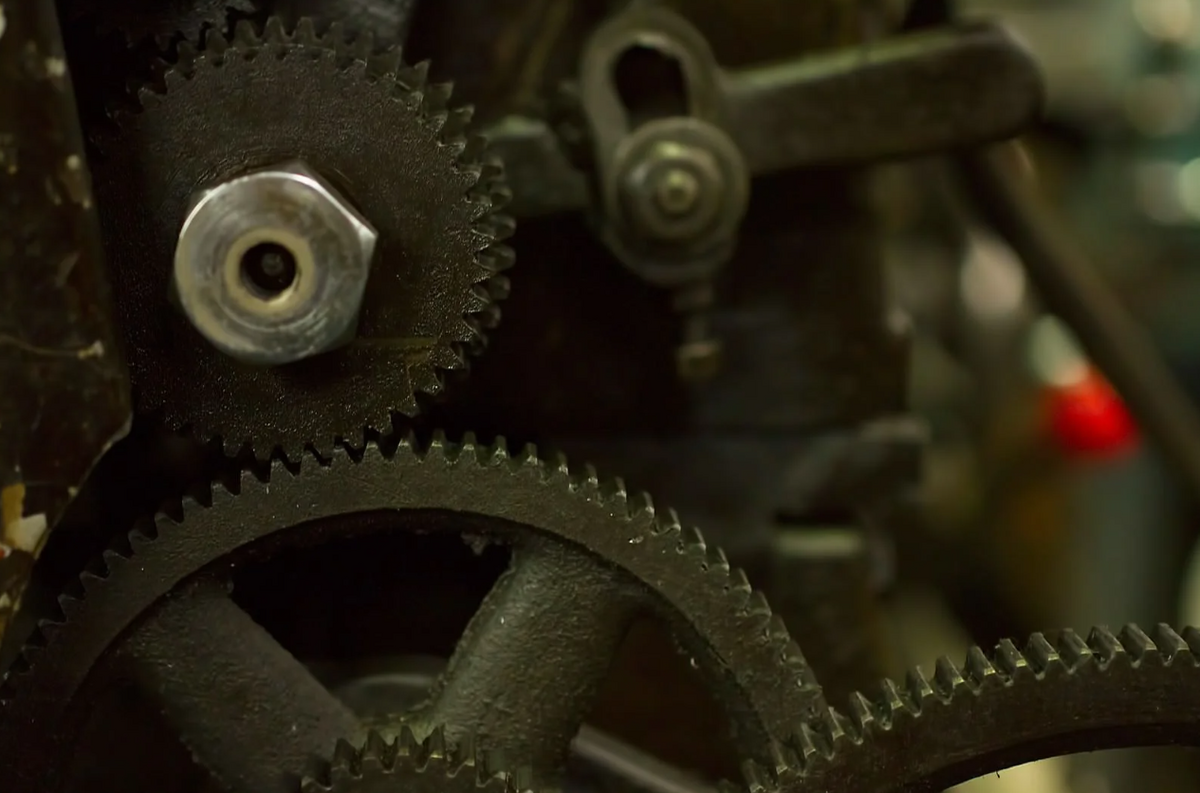
アドルノによればポピュラー音楽では全体的な計画性が衰退し、
私は音楽理論は専門外なので、
さらにアドルノは、ポピュラー音楽が「気晴らし(

気晴らしの概念は、個人心理学における自給自足の術語ではなく、
令和の音楽は超短時間の刺激を提供する
アドルノはポピュラー音楽を手厳しく批判したが、
私が最近注目しているのは、式浦躁吾という作曲家である。
古き良き時代のシリアス音楽には全体的な計画性があり、
最近、

コンテンツの倍速視聴が流行する理由は他にもたくさん考えられる
ハイデガー選集13『世界像の時代』解説や考察みたいなもの

ハイデガー選集13『世界像の時代』
ハイデガー(桑木務訳)
昭和37年1月25日発行
世界……像……そして世界像
『世界像の時代』を解読するためには、ハイデガーが「世界」
 マルティン・ハイデガー(1889~1976)
マルティン・ハイデガー(1889~1976)
このばあい世界とは、存在するものをひっくるめての名称です。
んでもって次は、「世界像」の定義を見ていこう。

像とはこのさい、試し刷りといったものではなくて、たとえば、
近代……中世……そして輝かしい古代
ハイデガーによれば、中世(ヨーロッパ)では存在するものが「

近代物理学は、それが優れた意味において、
ハイデガーは、

ギリシア精神は、存在するものの近代的解釈から、
ハイデガーはこの『世界像の時代』で、
「強い言葉」が「重要な言葉」だとは限らない

『世界像の時代』の「補遺」には、「宇宙的(惑星的)帝国主義」
「宇宙的(惑星的)帝国主義」という術語の響きや意味合いは、“
